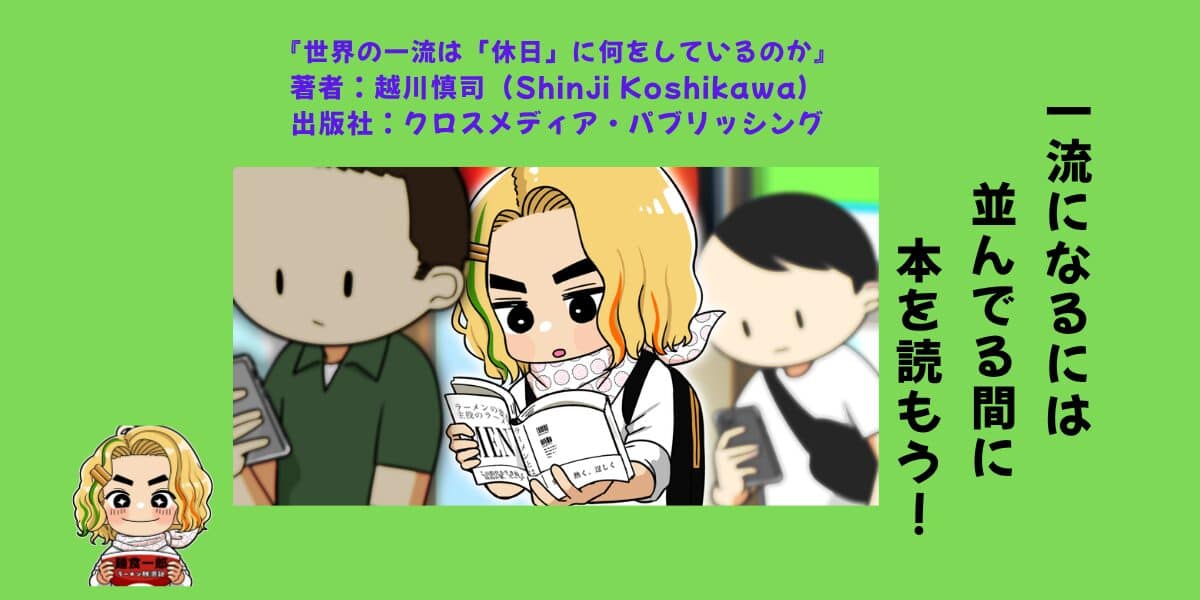1 待ち読書とは
行列のできるラーメン屋に並んでいる時、皆さんは何をしているだろうか。
多くの人はスマホをいじって時間を潰しているが、この待ち時間こそ人生を豊かにする絶好の機会である。
私はこの時間を「待ち読書」に充てている。特におすすめしたいのは「紙の本」である。理由は明快で、太陽光の下でも読みやすく、充電不要で持ち運びが容易だからである。電子書籍も便利であるが、ラーメン待ちには紙の本の方が適している。
ラーメンを待ちながら本を手に取り、無駄と思われがちな時間を「生きた時間」に変える。これこそが「待ち読書」の真髄である。
2 『世界の一流は休日に何をしているのか』越川慎司
待ち読書で大いに参考になったのが、越川慎司氏の 『世界の一流は休日に何をしているのか』(日本能率協会マネジメントセンター) である。
まずタイトルが秀逸である。「世界の一流が休日に何をしているのか」という問い自体が好奇心をかき立てる。もし私が一流であるならば、「世界の一流は休日にラーメンを食べている」ということになるのだろう。
著者によれば、一流の人々は休日を「チャレンジデー」と位置づけ、仲間との交流や趣味、セミナー参加など動的な行動に充てている。単なる休養ではなく、挑戦へのエネルギーを蓄える日としているのである。
特に印象に残ったのは「読書」に関する記述である。
- ビル・ゲイツは毎週1冊(年間約50冊)を読む
- 一流のビジネスパーソンは年間43.2冊を読む
- 平凡な人の平均読書量は年間2.4冊にすぎない
この差が格差社会を生み出す一因ではないかと著者は指摘する。私はこの事実に強く衝撃を受けた。
3 待ち読書の効果
仮に月8回ラーメン屋に通い、1回あたりの待ち時間を1時間とすると合計8時間になる。文庫本(約300ページ)はおおよそ8時間で読了可能である。すなわち、ラーメンの待ち時間を使うだけで月1冊の本を読むことができるのだ。
読書によって知識や思考は深まり、一流に近づく。学びが豊かさを生み、その豊かさでまた美味しいラーメンを食べる。そして再び待ち時間に本を読む。
この循環を繰り返すことで、ラーメンを楽しみながら一流に近づけるのではないかと私は考えている。
まとめ
- ラーメン屋の行列時間は「待ち読書」に最適
- 紙の本は読みやすく、充電不要で実用的
- 一流の人々は休日を能動的に使い、読書量も圧倒的に多い
- 月8回ラーメンに通えば「月1冊の本」を読める
ラーメンとの出会いの時間が、人生の学びの時間へと昇華する。これからも「待ち読書」を通じて、心と人生をさらに豊かにしていきたいと思う。